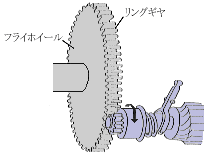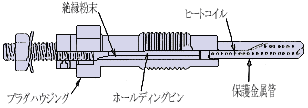自然界に存在するさまざまなエネルギーを機械的な仕事(力学的エネルギー)に変換する装置を原動機といいます。
原動機は、ガソリンや軽油等の燃焼エネルギ、蒸気の熱エネルギ、電気エネルギを機械的エネルギに変える装置で、移動式クレーンには主に内燃機関と油圧装置が用いられている。油圧装置は、一次原動機の内燃機関のエネルギを油圧に変換し、そのエネルギを更に機械力に変えることから、二次原動機と呼ばれている。内燃機関には、軽油を燃料とするディーゼルエンジンと、ガソリンを燃料とするガソリンエンジンがある。 内燃機関は、機動性が要求される移動式クレーンに最も適した原動機といえる。移動式クレーン以外のクレーンの原動機には、三相誘導電動機が多く使用されている。
 |
ディーゼルエンジンは、「ルドルフ・ディーゼル(1858〜1913)」に よって発明された。 ルドルフ・ディーゼルは、数々の失敗をくり返したの ち、1892年に「今日知られている蒸気エンジンと内燃エンジンに取って代 わる合理的熱エンジンの理論と設計」という論文を発表し、翌年、ドイツ の特許を得た。 |
ルドルフ・ディーゼルの論文には、燃料と空気を別々に燃焼室に送り込み、混合気の発生と共に燃焼させる「不均一混合」の原則、爆発に点火プラグを使わない 「自己着火(圧縮着火)」の原則というディーゼルエンジンの基本原理が書かれている。ルドルフ・ディーゼルのディーゼルエンジンは、圧縮比や爆発圧力が高いため、騒音や振動が大きく、エンジンの各部を頑強に作る必要がある。頑強なゆえに耐久性には優れているが、エンジン全体の質量が増す傾向がある。また、精密で高圧な燃料噴射装置、始動時に必要な大容量のスターターやバッテリー等の採用により、エンジン価格は高くならざるを得ない。
同じ排気量のガソリンエンジンと比較した場合、ディーゼルエンジンは重量があるため、高速回転に制約を受け、エンジン出力は低くなる。その反面、内燃機関の中では最も熱効率に優れている。熱効率とは、燃焼時の熱量を動力に換算した比率で、熱量に対して動力に変わる割合が大きいというメリットがある。更に燃料である軽油は引火点が高いため、火災につながる危険性が少ない。高負荷高圧縮比の燃焼に耐える頑強な構造により、一般のガソリンエンジンと比べて耐久寿命が約3倍もある。点火装置が不要なため、電気系統のトラブルが少ない等の信頼性にも優れている。このため、現在の移動式クレーンには、燃効率が良く、燃料経費が安い直接噴射式ディーゼルエンジンが多く使用されている。
| エンジンの比較 | ディーゼルエンジン | ガソリンエンジン |
| 燃 料 | 軽油・重油 | ガソリン |
| 着 火 | 空気圧縮による着火 | 電気花火による着火 |
| エンジン質量(馬力当り) | 大 | 小 |
| エンジン価格(馬力当り) | 高い | 安い |
| 熱効率 | 良い(30〜40%) | 悪い(22〜28%) |
| 経 費 | 安い | 高い |
| 火災の危険度 | 少ない | 多い |
| 騒音・振動 | 大きい | 少ない |
| 冬季の始動性 | やや悪い | 良い |
ディーゼルエンジンとガソリンエンジンは、外見及び構造はよく似ているが、ガソリンエンジンは混合気をスパークプラグの電気火花によって着火させるのに対し、ディーゼルエンジンは空気を圧縮して高温になったところに燃料を噴射して自然発火させる点が大きく異なる。エンジンは、密閉されたシリンダー内をピストンが繰り返して往復運動をすることで生じる力をコネクチングロッド、クランク軸で回転運動に変える。吸入、圧縮、燃焼、排気の1循環を1サイクルと呼び、1サイクルを4行程で行うものを4サイクルエンジン、1サイクルを2行程で行うものを2サイクルエンジンという。
2 サイクルディーゼルエンジンは、吸入、圧縮、燃焼、排気の1循環をピストンの2行程で行うもので、クランク軸が1 回転するごとに1回の燃焼が行われる。ピストンが下降して吸入口が開き、シリンダ内に過給機で強制的に新鮮な空気を送り込み、それと同時に燃焼したガスを外に押し出す。ピストンが上昇し始めて吸入口が閉じると、更に上死点までピストンが上昇して空気が圧縮される。圧縮されて高温となった空気に燃料を噴射し、自然発火により燃焼(爆発)させてピストンを下降させる。
4サイクルディーゼルエンジンは、吸入、圧縮、燃焼、排気の1循環をピストンの4行程で行うもので、クランク軸が2回転してカム軸が1回転するごとに1回の燃焼が行われる。
1. 吸入
吸入バルブが開き、ピストンが上死点(最上昇の位置)から下降する間に、シリンダ内に
空気が吸い込まれる。
2. 圧縮
吸入バルブが閉じ、ピストンが下死点(最下降の位置)から上昇する間に、吸入行程で吸
い込まれた空気が圧縮されて高温になる。ディーゼルエンジンは、空気の体積を1/20前後に
圧縮して600度以上の高温にしている。
3. 燃焼
圧縮されて高温となった空気に燃料噴射ポンプで100気圧以上に圧力を高めた燃料を噴射
し、自然発火で燃焼(爆発)させてピストンを下降させる。
4. 排気
ピストンが燃焼によって下死点まで下がると排気バルブが開き、ピストンが下死点から上
昇する間に燃焼したガスが排出される。
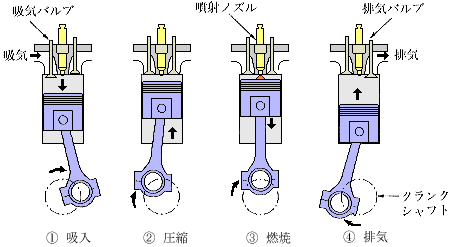
ディーゼルエンジンは、エンジン本体の他に過給器、タイミングギヤ、クランクシャフト、フライホイル、吸気装置、燃料装置、排気装置、潤滑装置、冷却装置、電気装置等によって構成されている。
エンジンの出力を上げるためには、密度の高い空気をどれだけ大量にエンジンに取込めるかが鍵となる。過給器は、圧力の高い空気をシリンダ内に強制的に送り込む装置で、排気の圧力でタービンを回転させて駆動させる方式と、エンジンのクランクシャフトから動力を得る方式がある。
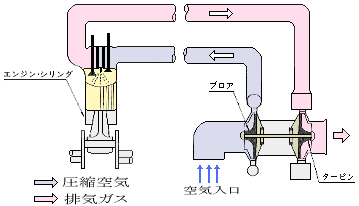
空気の吸入と燃焼ガスの排出には、各工程の必要な時期にバルブが開閉する必要がある。タイミングギヤは、クランク軸の回転をカム軸に伝え、各カムの突起部分がそれぞれのプッシュロッドを押し、バネの力によって閉じているバルブを時期に合わせて開閉する。吸入と排気バルブの開閉の時期は、カム軸とクランク軸の間に組み込まれているギヤの噛み合いで決まる。 また、噴射ポンプの噴射時期もタイミングギヤによって制御している。
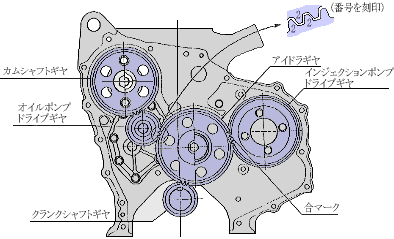
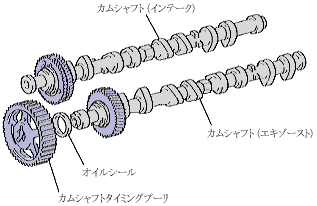
クランクシャフトは、ピストンの往復運動を回転運動に変えるもので、コンロッドによってピストンとクランクシャフトをつないでいる。フライホイルは、クランクシャフトのトランスミッション側に取付けられている円盤状の回転体で、いつまでも回り続けようとする慣性力を利用してクランクシャフトの回る勢いを保ち、回転むらを小さくするためのはずみ車としての役目を果たしている。エンジンを始動させる時は、フライホイルのリングギヤにスタータのピニオンを噛ませ、クランクシャフトを回しエンジンを始動させる。
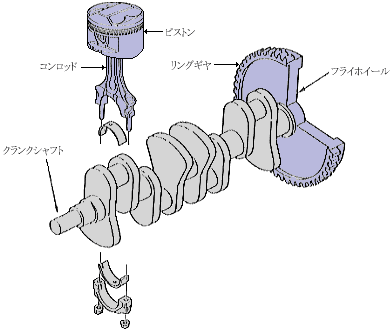
燃焼に必要な空気は、エアクリーナ、インテークマニホールド、吸気バルブ、シリンダの順に流れる。
1. エアクリーナ
エアクリーナは、大気中のごみや埃をろ過する装置である。 エアクリーナの汚損は、出力
を低下させ、ピストンやシリンダの磨耗を早るため、一定期間ごとに清掃、洗浄又は交換す
る必要がある。
2. インテークマニホールド
エアクリーナから吸気バルブまでの吸気菅をインテークマニホールドという。
3. 吸気バルブ
シリンダヘッドには、空気の吸入と燃焼ガスの排出のためのバルブが取付けられている。
バルブは、常にバネの力で閉じており、カムで押されて開く構造である。
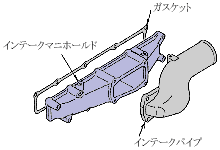
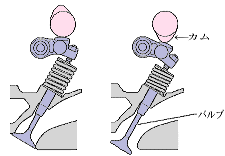
ディーゼルエンジンの燃料は、燃料タンク、燃料供給ポンプ、燃料フィルタ、燃料噴射ポンプ、燃料噴射ノズルの順で流れ、シリンダ内の圧縮されて高温となった空気に噴射される。エンジンの停止は、噴射ポンプへの燃料の供給をカットして停止している。
1. 燃料噴射ポンプ
燃料噴射ポンプは、ガバナで燃料の噴射量を調整し、高圧の燃料を燃料噴射ノズルに送る
ものである。ディーゼルエンジンは、空気の量は変わらず、噴射する燃料の量によって出力
を調整している。
2. 燃料噴射ノズル
燃料噴射ポンプから送られた高圧の燃料を微細な霧状にして、燃焼室へ噴射する装置を燃
料噴射ノズルという。
3. 燃料フィルタ
燃料フィルタは、燃料をろ過して混入しているカーボンの粒子や金属粉等のゴミを取除き
燃料噴射ポンプや燃料噴射ノズルの不具合の発生を防ぐものである。
シリンダ内で燃焼したガスは、排気バルブ、エキゾストマニホールド、エキゾストパイプ、マフラを経て大気中に排出される。
1. エキゾストマニホールド
各シリンダが出す燃焼ガスを集合させるパイプ
2. エキゾストパイプ
エキゾストマニホールドとマフラを繋ぐパイプ
3. マフラー
エキゾストマニホールドから送られたガスをそのまま大気中に放出すると、急激な膨張に
よって大きな騒音を発する。マフラーは、高い圧力で流れてきた排ガスの圧力を下げ、吸音
材によって騒音を小さくしている。
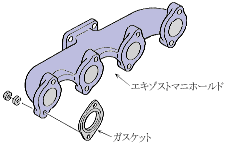
潤滑装置は、エンジンのシリンダ壁(シリンダライナー)、ピストンリング、各部の軸受等に潤滑油(エンジンオイル)を与えて磨耗や焼付きを防止している。クランクケース下部のオイルパンの潤滑油をオイルポンプによってオイルフィルタ、オイルクーラ、各潤滑部に順に送り、再びオイルパンに戻す。各部品の金属が直接触れ合って回転運動や往復運動を繰り返すと金属の表面が擦れて磨耗したり、高温になって焼付きを起こす。潤滑油は、ミクロン単位の油膜を作り、金属同士が直接触れないようにする働きがある。潤滑油は、磨耗や焼付き防止の他冷却、清浄、密封、腐蝕防止の作用があり、機械効率を高めている。
1. オイルポンプ
オイルポンプは、潤滑油を各部へ送る役目を果たすもので、クランクシャフトギヤにより
アイドルギアを介して駆動している。
2. オイルクーラ
オイルクーラは、エンジン各部へ運ばれるオイルを熱交換器の中に通して冷却し、適度な
温度を保つために設けらている。
エンジンは、シリンダ内で燃焼が繰り返し行われて高温になる。冷却装置は、高温になったシリンダを冷却するもので、空冷式と水冷式がある。空冷式は、シリンダの外側に空気に触れる面積を大きくした冷却ひれを設け、これに風を受けて放熱する。移動式クレーンに使用されている冷却装置は、エンジンシリンダの外側に水の流れる通路であるウォータジャケットを設け、ラジエータからの冷却水をウォータポンプ、エンジン各部、サ−モスタットへと循環させている。
1. ラジエータ
ラジエータには、放熱体のラジエータコア、冷却液を蓄えるタンク、ラジエータに風を送
る冷却ファンが設けられている。冷却液は、やむを得ない場合を除き水道水は使用せず、水
と凍結防止剤等を配合したロングライフクーラントを使用する。
2. ウォータポンプ
ウォータポンプは、冷却装置内を流れる冷却液を循環させる装置で、ファンベルトからの
動力で羽根を回転させて水流を作っている。
3. サ−モスタット
サ−モスタットは、冷却装置内を流れる冷却液の温度を見極め、冷却液をラジエータに流
す又は、そのままエンジンに循環させるのかをコントロールするバルブである。
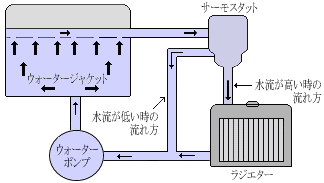
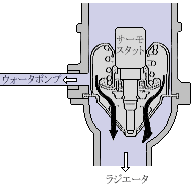
ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンに使用する点火装置は必要ないため、一度始動すれば電気装置がなくても動き続けることができる。
1. バッテリ(蓄電池)
バッテリは、スターティングモータやヒータプラグ等の電源となる蓄電池で、電気を蓄え
る充電作用と、蓄えた電気を使用するために放出する放電作用を化学反応によって起こして
いる。バッテリは、セルの中に陽極板と陰極板を向かい合わせ、電解液の希硫酸を満してい
る。希硫酸の水分は蒸発するため、液面が上限と下限の間にあることを確認する。不足して
いる場合には、各セルの液面のレベルまで蒸留水を補充する。寒冷地で長期間運転をしない
場合は、低温では容量が低下するため、機体から取外して保管する。バッテリを取外す場合
は、スパナ等でショートしないように注意しなければならない。移動式クレーンは、12Vの
バッテリ2つを直列に配列し、24Vにして使用している。
2. スターティングモータ(スタータ)
スターティングモータは、回転軸にピニオンを備え、スタータのスイッチを入れると、モ
ータが回転すると同時にマグネットスイッチが働いてレバーを引き、ピニオンが飛び出して
エンジンのフライホイールのリングギヤに噛み合い、フライホイールを回転させてエンジン
を始動させる。ピニオンは、始動が完了すると噛み合いが外れて元の位置に戻る。
3. オルタネータ(交流式直流出力発電機)
オルタネータは、エンジンの回転をファンベルトで受けて駆動する。各種電気装置に使わ
れる電気は、オルタネータで発電され、一部はバッテリに蓄えられる。ACジェネレータと呼
ばれる交流発電機で交流を発生させ、内蔵している整流器と電圧調整器(レギュレータ)で
電圧の制御を行って適正な直流電流を出力している。
4. 始動補助装置
エンジンの寒冷時の始動を容易にするため、燃焼室又は吸気を暖め着火の手助けをする装
置を始動補助装置という。始動補助装置には、副室式エンジン内を加熱するグロープラグと
直接噴射式エンジンのマニホールド内の吸気通路に取付け、発熱体に電気を通して吸気を均
一に加熱する電熱式エアヒータの方式がある。